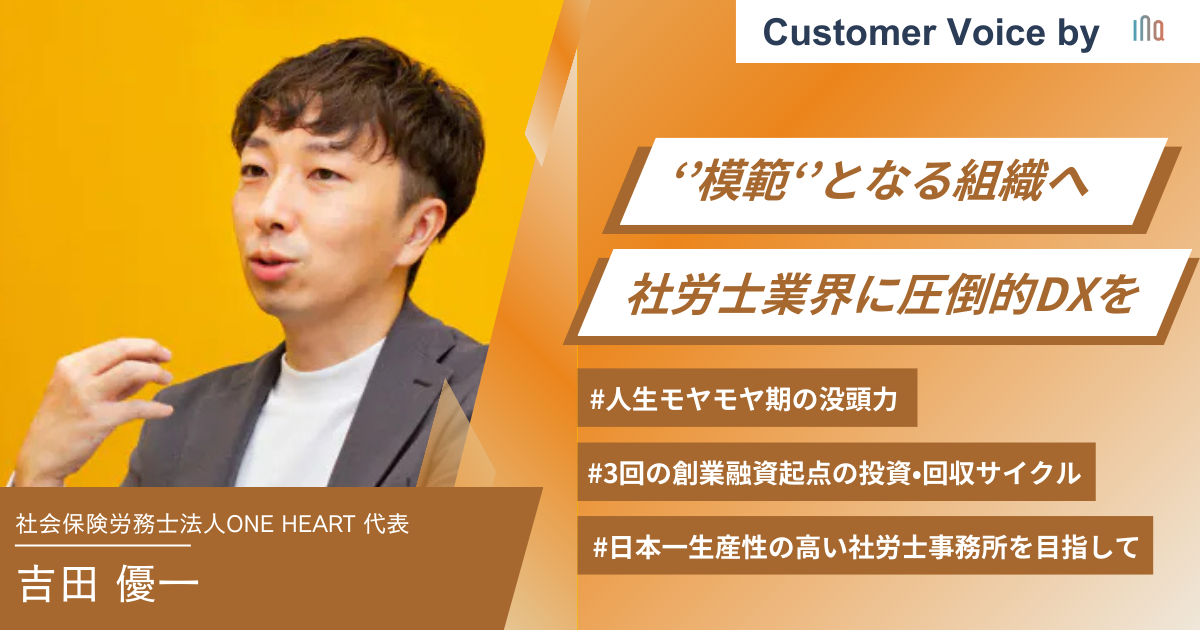Newbee株式会社
蜂須賀 大貴
「メディア×テクノロジーで市場を創る」──ユーザーフレンドリーを守るために選択した創業融資
2025年8月30日

テクノロジー領域において、エンジニア不足や採用難が語られる一方で、裾野となる最前線の知見を届ける「勝ち切れたメディア」は存在しない──。
そんな課題感から誕生したのが、テクノロジーメディア『Newbee』を運営するNewbee株式会社。
代表の蜂須賀さんは、イマジカでのエンジニア・技術営業経験、フリーランスを経て、サイカやPIVOTでプロダクトマネージャーとして活躍。大企業から数人規模まで多様な組織を渡り歩き、役割もメンバーからマネジメント、そして経営へと拡張してきました。
創業期のファイナンスでは、広告収益モデルのジレンマを踏まえ、融資を実行。現在、創業年度から躍進を続けています。
そんな蜂須賀さんのキャリアの軌跡、メディア事業特有のファイナンスの考え方、そして「日本のテクノロジーを外側から強くする」というビジョンについて伺いました。
Newbee株式会社 代表取締役 蜂須賀 大貴 ・X
株式会社IMAGICA(現:IMAGICA Lab.)でエンジニアとしてキャリアをスタート。フリーランスPMとして複数企業の支援を経て、株式会社サイカにてプロダクト戦略の立案と実行をリードし、事業成長を牽引。その後、PIVOT株式会社にて、プロダクトマネージャー兼プロダクト組織の立ち上げを担当し、成長スタートアップ特有の課題解決やプロセス構築に携わる。現在は、2025年3月にNewbee株式会社を創業。テクノロジーメディア「Newbee」の運営、プロダクト支援、開発組織支援を行う。
目次
メディア×テクノロジーを歩んだ試行と深化
interviewer:
まずは、蜂須賀さんのキャリアの出発点からお伺いさせてください。
蜂須賀さん:
子どもの頃からテレビが大好きで、いわゆる「テレビっ子」でした。
その延長線上で大学では情報系の学部に進み、CGを研究していました。映像表現の可能性に触れるうちに、メディアとテクノロジーの両方に強い関心を持つようになったんです。
そんな中、就職活動期に東日本大震災が発生しました。採用が止まったり内定取り消しが相次いだりと、ご認識の通り社会全体が混乱していました。
世の中では「エンタメは不要不急」とされがちでしたが、わたしは逆にそうした文化が失われていくのはとても悲しいと感じました。むしろ人の心を支える力があるからこそ必要なのだと思い、改めてメディアに携わる使命感を強めました。
そんな想いから、2012年に新卒で、映画・テレビ・アニメなど幅広い映像コンテンツの制作・編集・配信を手掛けるポストプロダクション企業、イマジカに入社しました。
interviewer:
イマジカでは具体的にどんな業務をされていたのですか?
蜂須賀さん:
配信事業の部署でエンジニアとして働きました。
当時はNetflixがまだ日本に来ておらず、Amazon Primeが始まったばかり。テレビ局や映画会社と連携し、海外プラットフォーマーが日本に参入する際の仕組みづくりを担当しました。たとえば、コンテンツ権利のオンライン売買システムや、納品先ごとの動画形式変換、出演者データの加工などです。
また、東京国際映画祭や香港フィルマートなど国際映画祭にも出向き、英語でシステム営業を行ったこともあります。エンジニアでありながら泥臭い営業を経験できたのは大きな財産でした。このほかにも、開発チームの内製化や事業開発も経験し、社内で幅広い役割を担うようになりました。
その一方で、終盤には社外で登壇する機会やメディア露出も増え、外の人たちから声をかけていただくことが一気に増えたんです。「外で自分がどれだけ通用するのか」を確かめたい気持ちが次第に強くなっていきました。
ちょうどその頃、野球のFA制度に触発され、自分のYouTubeチャンネルで「FA宣言」をしてみたんです。
interviewer:
「FA宣言」というのは?…
蜂須賀さん:
野球選手が一定の年数を経て「フリーエージェント(FA)」になり、自分から「どこの球団とも交渉できます」と表明する制度があるんです。私はそれになぞらえて、自分のYouTubeで「私はフリーになりました。興味があれば声をかけてください」と宣言した、というわけです。あえてYouTubeを選んだのは、文章より動画の方が自分の温度感や雰囲気を直接伝えられると思ったからでした。
すると想像以上の反響があり、約50社からオファーをいただきました。正直、自分でも驚きましたね。「本当に必要とされているんだ」と実感できた瞬間でした。
複数社と同時に関わることで新しい視点を得られるのではと考え、またメディア以外の領域にも挑戦して視野を広げたいという思いもあって、フリーランスを選びました。
interviewer:
フリーランスではどんな活動をされたのですか?
蜂須賀さん:
主にプロダクトマネージャーとして活動しました。
ただ、契約は3〜6か月の短期が多く、プロダクトの2〜3年先を見据えるのは難しかったんです。中長期的に伴走しようとお客様の声を聞いていくと、「プロダクト戦略を考えて、実行してほしい」ではなく「内部のメンバーを育ててほしい」というニーズが増えていきました。
その結果、次第に「開発よりもメンバー育成をしてほしい」という要望の比重が高くなり、本来自分がやりたい「ものづくり」とのギャップを強く感じるようになりました。そこで改めて正社員として腰を据えて取り組むことを決め、マーケティング領域でデータ解析を強みとするスタートアップのサイカに入社しました。
interviewer:
所属の形を変えた経験が、ご自身の志向を確かめるきっかけになったのですね。
蜂須賀さん:
まさに。サイカでは新規事業のプロダクトマネージャー責任者として、未来構想や戦略を描いていました。その中で大きな学びとなったのは、「外部人材に頼るのではなく、内部の人材を育てることが持続的な強さにつながる」という点です。これは今の自分の考え方にも直結しています。その後、サイカが上場に向けて成長戦略を転換し、コンサルティング事業へ注力することになり、自分にとっても新たな挑戦の契機だと感じました。
ちょうどその頃、私はビジネス映像メディア『PIVOT』のユーザーでもあり、代表の佐々木さんのファンでもありました。当時、プロダクトマネージャーのポジションが空いていると知り、即応募。ご縁があって入社することになりました。
PIVOTではプロダクトマネージャーを務めながら、外注中心だった開発を内製化し、初のエンジニアとして開発組織を立ち上げました。チームづくりからプロダクト戦略まで幅広く関わり、実質的にはCTOやCPOのような統括的な役割も担っていました。
interviewer:
なるほど。役割に伴って多様な組織規模をご経験されていますね。
蜂須賀さん:
イマジカは2,000人、サイカが200人、Pivotが20人、そして起業した今の会社は2人。
組織規模がゼロひとつずつ減っていきました。その中で、役割もメンバー→マネジメント→経営と広がり、見る範囲がプロダクトから経営全体へと近づいていったと感じています。
テクノロジー領域にメディアの入口を──PIVOTでの学びと創業前の確信
interviewer:
その後、2025年3月に創業という経緯ですね。起業のきっかけを教えてください。
蜂須賀さん:
PIVOTでの経験から「メディアが市場を創り出す力」を実感したことが、大きなきっかけのひとつです。
ただ、テクノロジー領域には勝ち切れているメディアがなく、記事媒体は多くても動画や音声はまだ少ない。「片手落ち」だと強い問題意識を持ちました。エンジニアコミュニティは充実しているのに、その入口となるメディアが足りていない。
本来、メディアは新しい人材や企業が情報を得て参入する「入り口」として機能し、そこから実践・発表・共有へと循環が生まれることでエコシステムが回り始めます。ところが、この入口が弱いままでは、コミュニティの内側だけで盛り上がっていても、外からの参加や知識の循環が起こりにくく、市場形成が加速しないと考えています。
このエコシステムを構築できるのは、メディアとテクノロジーの両方を理解している人間が望ましい。だからこそ「自分がやるしかない」と思ったんです。
もうひとつの視点は、PIVOTで経営に近い立場を経験したことにあります。経営に直結する意思決定の現場を間近に学べたのは本当に貴重で、大きな財産になりました。その過程で、「AIなどのテクノロジーを経営のど真ん中に据える意思決定は、やはりテクノロジー出身の経営者が担うことでより機能する」と強く感じたんです。
その結果、自然に「自分が経営者になるしかない」という結論に至りました。
interviewer:
目指すものを、自分が担う必然だと受け止められたのですね。事業アイディアの検証はどのように実施したのでしょうか?
蜂須賀さん:
2025年1月頃から、多くの人に相談し、いわゆる「壁打ち」をしてもらいました。様々な人に意見をもらいながら自分の考えをぶつける中で、ほとんどの方から肯定的な反応をいただいたんです。
前述したようにPIVOT在籍時から、需要も供給も明らかに存在しているのに「テクノロジー領域で勝ち切れているメディアがない」という現実を強く意識していました。壁打ちを重ねることで、この問題意識が単なる思い込みではなく、多くの人に共通して認識されている課題だと確認できたんです。
その確かさが「これは確実にニーズがある」と背中を押し、創業に踏み切る決定的な要因となりました。
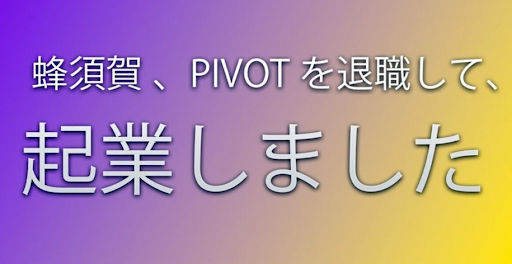
起業時、想いを綴った蜂須賀さんnote
メディアの入口から社会へ──広がるターゲットと現場との接点
interviewer:
改めて、現在の事業について教えてください。
蜂須賀さん:
大きく三本柱で展開しています。
まずひとつ目はメディア事業です。自社のYouTubeチャンネル、テクノロジーメディア『 Newbee』を運営していて、AIやエンジニアリング、CTOインタビューなどを発信しています。おかげさまで「現場のリアルが聞ける」「難しい技術が理解しやすい」といった声をいただいています。そこから派生して、企業から制作受託やコンテンツ支援の依頼もいただくようになりました。
二つ目はプロダクト開発支援です。特にアーリーフェーズの企業から「どう進めていいかわからない」というご相談をいただくことが多いですね。代表が非エンジニア出身のケースも珍しくないので、最初のプロトタイプを一緒につくったり、開発の進め方を壁打ちしながら伴走することが多いです。
一方で、レイターフェーズの企業になると、すでに開発チームはあるので、そこをどう強化するかがテーマになります。たとえば、メンバー育成や組織全体の戦略を整理し、よりスケールできる体制に整えるといった支援にシフトしていきます。
直近の事例としては、『TVer』を運営する株式会社TVer様の開発プロセス改善をご支援させていただきました。
PdMやエンジニアリングマネージャーと一緒にアジャイル開発のワークショップを実施し、知識を組織全体にインプットしたうえで、理想的なチームを一つつくり成功事例を横展開する取り組みを進めています。組織の急拡大によるスピードと品質のバランスの課題に対し、「守り」と「攻め」の両面を整理するサポートを行いました。こうした取り組みはまさに、レイターフェーズの組織を強くする支援の典型例だと思います。
三つ目は開発組織支援です。会社が成長すると「採用はできたけど組織がバラバラ」という課題が出てきます。どんな人を採用すべきか、自社文化に合う人材像は何かを一緒に考え、採用戦略を立てて実行します。既存組織のマネジメント改善をサポートすることもありますね。
interviewer:
3つとも、まさにこれまでのキャリアで積み上げてきた知見が活きていますね。
蜂須賀さん:
そうですね。意識しているのは「メディアとそれ以外につかう私のリソースを半々にする」ことです。
メディアだけに偏るとどうしても現場感覚を失いがちになりますが、プロダクト開発や組織支援を実際に手掛けることで、肌感覚を保ち続けています。
interviewer:
メディア事業では対象がエンジニアのほかに、学生や主婦層も意識されているとか。
蜂須賀さん:
はい。AIが日常に溶け込む今、テクノロジーを理解しているか否かでキャリアや生活に大きな差が生まれます。学生であれば進路選択が180度変わる可能性があるし、主婦の方にとっても子育てや生活の中で避けて通れない領域になっています。
だからこそ「テクノロジーは一部の専門家だけのものではない」というメッセージを届けたいんです。ある意味、小学校でダンスが必修になったのと同じように、得意でなくても必ず触れるべき領域。それを理解する最初の入口として、動画や音声を通じて届けていくことに意義があると考えています。
interviewer:
なるほど。創業後、数か月 現在のフェーズで経営として大事にしていることは何でしょうか?
蜂須賀さん:
今はとにかく認知フェーズだと捉えています。メディアは無数にあり、AIで自動生成された記事すら溢れている時代です。その中で本当に価値あるものをどう届けるかが問われます。
だからこそ「誰かのニーズに刺さるコンテンツを常に提供し続ける」ことを経営のど真ん中に置いています。メディアでも支援事業でも、最終的に求められるのは「価値をつくり続けられるか」だと考えています。

ユーザーフレンドリーを守るために──エクイティではなく融資で進めた理由
interviewer:
ここからはファイナンスについて伺いたいと思います。創業前、資金面で意識されていたことはありましたか?
蜂須賀さん:
これは過去のキャリアを通して実感したのですが「メディア事業とエクイティ調達の相性はあまり良くない」ということを感じていました。
一般的には、シリーズA程のフェーズで黒字化していたらエクイティ支援いただいたVCの方から評価いただくことが多いと思うんです。でも、メディアの場合はそう単純ではありません。たとえば、広告収益モデルで番組の中にスポンサード番組の割合が高まり、視聴者の方から「広告が増えてつまらなくなった」という声をいただく場合もある。つまり、収益を伸ばすことが必ずしもユーザーに歓迎されるわけではない、というジレンマがあるんです。
interviewer:
確かに、メディアのビジネスモデル如何ですが、広告収益で、実際広告に寄りすぎるとメディアの信頼性が損なわれるケースはありそうです。
蜂須賀さん:
そうなんです。
また、グロース市場の上場維持基準の改定など、環境の変化はありますが、一般的にVCの方からエクイティで資金調達をすると、7〜10年でのイグジットを前提に急成長を目指すことになります。
しかしメディア事業は、前述したジレンマから、無理にスケールさせようとするとユーザーフレンドリーさを損なうリスクがある。だからこそ、創業期は「エクイティは慎重に、まずは自己資金とデット(融資)で進めるべきだ」と、当初から考えていました。
interviewer:
実際、融資の検討ステップはどのように進めたのですか?
蜂須賀さん:
正直、全然詳しくなかったので、最初から専門家に相談しようと決めていました。
たまたま、INQの代表の若林さんとプライベートで行ったお店でお隣の席になったことからご縁があり、それがきっかけでINQを知りました。さらに、当時VCにいたパートナーからも「ファイナンスのことならINQが良い」と推薦をもらったんです。それで「もうINQ一択だな」と。結果的に、フリーランス事業を残していた関係で、創業融資制度は活用できなかったので、日本政策金融公庫の融資等で実行することになりました。
interviewer:
融資の資金はどんな用途を想定されていたのでしょうか?
蜂須賀さん:
一番大きいのはコンテンツ制作に関わる人件費です。
1本の動画を作るのにもカメラマン、ディレクター、編集者が必要で、チームで動く分コストがかかります。あとは初期の機材購入ですね。カメラや照明、編集用のPCなど、最低限の設備を揃えるために融資を活用しました。
interviewer:
結果的に、日本政策金融公庫様と湘南信用金庫様から計2000万円融資が実行されました。実行までの弊社とのやり取りはいかがでしたか?
蜂須賀さん:
最初の面談では、当初の希望額に対して「厳しそう」とフィードバックを受けました(笑)
そこから当社のビジネスモデルをより深く理解いただき「どうすれば希望額に近づけるか?」という議論を重ねるなかで、あらゆる方策を一緒に考えてくれました。最終的には、いずれの金融機関からも満額の回答をいただけたんです。あの時の安心感はとても大きかったですね。
創業期は、役所の手続きから顧客開拓、採用、ビジョン策定まで、やることが山ほどあり、すべてを創業者自身が抱え込みがちです。だからこそ経営者が本当に向き合うべきは「本質的な価値提供」だと思います。
ファイナンスはもちろん重要ですが、そこに向き合っている時間は頭の大部分を占めてしまいます。私のように直接的なファイナンス経験を持たない創業者にとっては、信頼できるパートナーに任せることが何より大切だと改めて実感しました。すべてを自分で抱え込む必要はないのだと。
日本のテクノロジーを「外側から強くする」──AI時代に挑むNewbeeのビジョン
interviewer:
今後のビジョンについてお聞かせください。
蜂須賀さん:
AIの波は抗えないほど大きなものだと思っています。日本の企業が海外勢に主導権を取られてしまうという視点ではなく、その企業本来の強さ、日本の企業だからこそのプロダクトの強さで勝負する。という視点で語りたいです。そのために私は「日本の企業を外側から強くする」ことを自分のミッションに据えました。
interviewer:
「外側から強くする」という表現は印象的ですね。
蜂須賀さん:
経営者の中に入り込んで全てを代わりにやるのではなく、エコシステムや仕組みを提供して強くなるための環境を整えるというイメージです。メディアがインプットの場を提供し、プロダクト開発支援が実践を伴走し、開発組織支援が長期的な体制強化につながる。
こうした要素が組み合わさることで、個社の成長が波及し、業界全体、日本全体の底上げにつながると考えています。
interviewer:
では、その構造をつくるために、最初のステップとして考えていることはありますか?
蜂須賀さん:
まずは小さくてもいいので拠点となるスタジオを持ちたいです。
今は機材をキャリーケースで運んでいて、すでに何度も壊れているので(笑)、効率も悪い。豪華なスタジオではなくても、安定して収録できる場を持つことが「メディアをきちんと育てる」という意思表示にもなりますし、クライアントとの共同制作や配信体験にも信頼感を生むと思います。
そして、その先には、メディアを基盤にした新しいプロダクト構想があります。テクノロジー領域だからこそ実現できる次のサービスであり、そこではエクイティも含めたファイナンスを活用しながら、より成長速度を高める選択を考えています。
interviewer:
起点はあくまでメディアでありつつ、その先にテクノロジーを軸とした世界観があるのですね。
蜂須賀さん:
はい。メディアは入口であり、同時に継続的な発信の力を持つものです。ここをまず確立させ、その先で日本企業の成長をさらに加速させる仕組みをつくりたい。
それが「日本のテクノロジーを未来永劫ブレないテーマとして強くしていく」という私のビジョンです。
*

※本記事は、取材時点の情報です
※インタビュアー・編集:株式会社INQ 遠藤 朱美
※デザイン:高橋 亜美
▼本プロジェクトのコンサルタント担当者

武田信幸
1981年生まれ。千葉県出身。
スタートアップの融資や補助金等による資金調達の専門家。
インストロックバンド「LITE」のギタリストとしても活動し、FUJI ROCKにも出演経験あり。年2,3回の海外ツアーをこなす「行政書士×ミュージシャン」のパラレルワーカー。 新しい世界に挑戦する起業家を支援。近年自身のバンドで補助金の採択を受け海外ツアーを行うなど、行政書士で得た知識を体現し、銀行融資に留まらず、補助金、出資等、様々な角度からアイデアを提供し、自身の経験を起業家へフィードバックする活動も行っている。