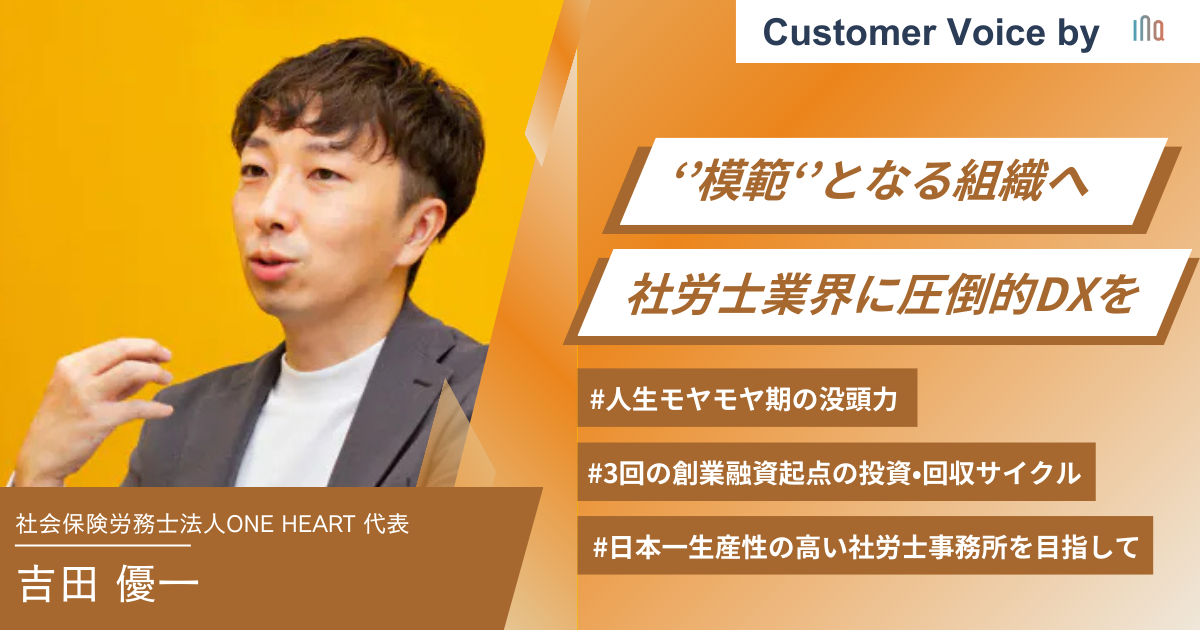株式会社bionto
妹尾浩充
異分野からの挑戦を強みに。技術を価値で届ける力になる ー ディープテック領域の創業期ファイナンスの選択肢 ー
2025年7月30日

2025年3月に創業した株式会社biontoは、東北大学発のディープテック領域スタートアップ。
独自の生体イオントロニクス技術によって、医療とヘルスケアの未来を描く同社は、創業からわずか2か月で事業会社との連携を進め、社会実装を着実に前進させています。
創業者の妹尾浩充さんは、映画プロデューサーとしてキャリアを始め、スタートアップでの事業開発経験を経て、研究者とともに起業へ。異分野出身を強みにし、研究と社会の翻訳者のような立ち位置で「技術を価値として届ける」という自身のミッションを、いかに築いてきたのか。
創業融資によって得られた成長資金、時間的・戦略的な余白により、スタートダッシュの軌道を実現しつつ、今後の調達にもつながっていく──。
そのプロセス、実感値とともに、これからの挑戦について伺いました。
株式会社bionto Co-founder/CEO 妹尾浩充
映画・コンテンツのマーケティングや企画制作、プロデューサーなどを経て、大手外資系企業にてコンテンツ配信ビジネスの立ち上げからマーケティングに従事。2019年、デジタルマーケティングのスタートアップに移り、シード期からPreシリーズCまでシニアビジネスプロデューサーとして事業開発を担当。2024年、東北大学ベンチャーパートナーズに客員起業家(EIR)として参画し、biontoを創業。
目次
映画からSaaS、そして事業開発へ──異分野で培った“ビジネス戦闘力”
interviewer:
まずは、妹尾さんのキャリアについて教えてください。
妹尾さん:
私のキャリアの出発点は、エンターテインメント・コンテンツの世界でした。プロデューサーの立場で、特に映画を扱うことが多かったのですが、監督やクリエイターの想いをどうカタチにして、どのように届けるかという視点で、作品づくりに徹底的に向き合ってきました。
最終的には、自分が向き合ってきた視点も含め、思い描いた映画をつくり届けるところまで辿り着けました。
ただ、映画はアートではなく“ビジネス”です。
なので良い作品ができても、それが収益として回収できなければ、次につながらないという現実もあります。
自分自身、作品づくりには一定の達成感を持ちながらも、「ビジネスとして成り立たせ続ける力」に課題意識が残っていました。
interviewer:
いわゆるビジネス戦闘力のようなスキルですか?
妹尾さん:
はい、まさに。そんなタイミングで、Amazon プライムビデオにジョインし、オリジナル企画に携わる機会を得たんです。
そこではまさに映画プロデューサー時代に感じていた「作品への愛情」と共にマーケティングや数字の裏付けといったビジネス視点がより必要だと痛感する環境でした。
異なるバックグラウンドを持ち、かつコンテンツ業界経験がない方々が、作品への想いと「ビジネス戦闘力」を持っているなと感じながら一緒に働く中で、改めて「自分もビジネスパーソンとしての筋力をつけ直す修行の機会が必要だ」と。
*
妹尾さん:
ビジネス戦闘力をより高めるため、「事業をつくる・会社をつくる」という視点で、チャレンジ機会を求めて飛び出すことを決意し選択したのが、スタートアップという環境です。
当時、社員が10人強で動画マーケティング事業等を展開していた株式会社リチカへジョインし、まさにゼロイチの事業づくり、組織づくりの真っ只中に飛び込みました。
シード期からシリーズAのフェーズで、SaaSプロダクトの販売や新規事業開発を担当し、事業開発責任者として、規模の大きな案件や新たなビジネスを創出する機会をリードさせてもらいながら、大変貴重な経験をしました。
interviewer:
フェーズからしても、事業・組織・資金・カルチャー等、とても変化が激しい時期だったと想像します。
妹尾さん:
はい、会社も急成長し、約5年間で社員数も120人を超えるところまできていました。
会社の急成長もあり、“もうひとつの山”を登ったような感覚がありました。
ちょうどその頃、AIなどの技術が一気に注目され始め、業界全体にも変化の兆しが見えてきたんです。
手触りある挑戦を求めて──ディープテックと“偶然の出会い”
interviewer:
ご自身の進化を追求しながら、キャリアを歩まれてきた中で、現在の起業という選択肢に至ったのは、なぜだったのでしょう?
妹尾さん:
ありがたいことに、やりたいことには恵まれてきたキャリアだったと思っています。
とはいえ、少しずつ芽生えた「このまま延長線上を歩き続けて良いのか?」という自分への問いも、無視せずに、心にとめてきました。
キャリアのはじめに課題意識があり、ビジネス戦闘力を高める歩みをしてきたからこそ、一度立ち止まって、自分が社会からどう評価されるのかを客観的に知りたいという想いもあり、数人のエージェントの方とお話しさせていただきながら、自分のキャリアを棚卸ししてみました。
すると、「ワクワク炎を燃やし続ける」ような新たなチャレンジを求めていること含め、自分への理解や気づきがありました。
interviewer:
自分への問いを見逃すことなく、見つめ続けたからこその、気づきだったのですね。
妹尾さん:
加えて、プライベートでも変化がありました。コロナを機に仙台に移住し、子どもの成長に伴い家族と共にする時間の捉え方が変わってきて、よりよい人生を過ごすため、家族との時間、環境、そして仕事を改めて大切にしたいという気持ちも強くなっていました。
その上で、「もっと手触り感のあることがしたい」と思い始め、世の中の根本的な課題解決につながる事業、例えばディープテックやグリーンビジネスといった分野への興味が強くありました。
しかし、自分が理系出身でもなく、キャリアに何かつながりがある訳ではないので、「こんな世界もあるんだな」という範囲、視野の拡大の意味合いに留まっていました。
ちょうどその頃、東北大学のベンチャーキャピタルである「東北大学ベンチャーパートナーズ(以降、THVP)」とのご縁がありました。
「スタートアップ5年計画」の中で、大学発スタートアップへの支援が強化され、事業を加速する上でのビジネス人材の必要性から、事業化を担うビジネスサイドのパートナーを探していると。
interviewer:
タイミングが運命的ですね。
妹尾さん:
はい、自分自身、それまで技術や研究とは縁のない人生でしたが、「やらない後悔」のリスクよりも「やったリスク」を取ろうと。
異分野からのチャレンジであることを十分自覚しつつも、培ってきたと捉えているマーケティング思考や顧客視点、ビジネス戦闘力があれば、ディープテック分野でも貢献できる、むしろ強みになると思いました。
そうして、2024年2月から1年間、THVPのプログラムに参加し、大学の先生と共同での起業を目指すことにしたんです。
健康長寿を支える“革新的なイオン制御技術”──医療とヘルスケアの未来をつくる
interviewer:
THVPへの参加を経て、今年2025年3月にbiontoを創業されました。
事業内容について教えていただけますか?
妹尾さん:
我々が取り組んでいるのは「イオントロニクス技術」と呼ばれる、新しい工学分野の技術を活用した事業です。特に「ロンジェビティ(健康長寿)」というテーマに焦点を当て、生体デバイスの企画・開発に取り組んでいます。
共同創業者でもある西澤教授は、東北大学の工学研究科に所属していて、人間の体内に存在する「イオンの動き」や「生命のメカニズム」をテーマに研究を続けてきた世界的な権威です。
健康に暮らしていく上での人体のメカニズムに精通するような技術基盤の研究を活かしながら、医療現場での治療からホームヘルス&メディカルケアまで広範囲に活用できるソリューションを提供して、より長く健康に生きられる社会の実現に貢献することを目指しています。
interviewer:
現状の事業フェーズはいかがでしょうか?
妹尾さん:
初期プロトタイプのデバイスが出来上がってきて、いよいよ商品開発フェーズに本格的に入ろうというタイミングに来ています。
同時に、大学と企業と我々の三者での共同研究というかたちも動き始めています。大学では種を育て、我々が花を咲かせ、協業先企業さまが市場に届けていく──そんな役割分担で、技術を社会に実装する仕組みをつくっていくことも目指しています。
interviewer:
協業先企業さまとは、どのような形で出会われたんですか?
妹尾さん:
大きく分けて3つのパターンがあります。
ひとつは、もともと大学の研究室と共同研究をしていた企業さん。スタートアップとして法人化したことで、より踏み込んだビジネス連携が可能になりました。
次に、論文発表や展示会などを通じてご興味を持っていただいたケース。
最後は、我々から積極的に提案していく、いわゆる“営業活動型”のアプローチです。
interviewer:
既に多様なパターンでの協業先企業さまとの連携が進んでいるのですね。

“餅は餅屋”は合理的な判断──ディープテック領域のファイナンス選択肢を狭めない
interviewer:
創業時点での資金調達については、どのように考えていらっしゃいましたか?
妹尾さん:
THVPでの活動を通じて、「いざ起業したら、資金はどう確保するのか?」という課題を常に意識していました。出資も当然候補にはありましたが、同時に創業融資のような選択肢もあると知り、資金調達のあり方を幅広くシミュレーションしていました。
正直なところ、ディープテックという領域もあり、最初は「エクイティしかないのかな」と思っていたんですよ。
でもあるとき、貴社Podcast『起業のデットファイナンス』に出会い、創業融資という制度の存在を知り、有効そうだと思いました。
interviewer:
なぜ、有効そうと思われたのですか?
妹尾さん:
私は、走りながら成長していくためには、ある程度の規模感で資金が必要で、そのためには出資という選択肢が濃厚かなと思っていた一方で、やはり十分な検討期間や準備の上で、出資先との出会いからパートナーシップを丁寧に築いていきたいと考えていました。
その選択肢を温めながら、数ヶ月しっかり走れるだけの資金を、着手してから約1〜2か月程の短期間で確保できるかもしれないと思ったからです。
interviewer:
最終的に創業融資をINQの支援を受けて実行しようと決めた理由を教えてください。
妹尾さん:
正直、それまでのキャリアで、資金調達の経験がなく創業融資という言葉に触れることすらなかったんです。
だから、プロのサポートを受けた方が間違いはないなという感覚はありました。
ただ、どんな感じで支援をしていただけるのか、最初はあまりイメージが湧かなかったんです(笑)
ですが、INQさんのPodcastを通して、「この人たちはこういうスタンスで支援してくれるのかな」と自然と納得感を持てました。
実際に担当いただいた片岡さんと話し、支援内容の明確さや幅広さにありがたい存在になるなと感じました。たとえば事業計画書の作成などでは、多数の成功事例を手掛けてきた専門家の知見やノウハウが、自力でやるよりもはるかに価値があると。
創業期は創業者自身でやることが多く、メンタルや体力も削られがちです。
そのなかで、“餅は餅屋”の考え方で、専門家の力を借りるという判断は、結果的にとても合理的な判断でしたし、現在は「信頼できるファイナンスパートナー」として、エクイティ調達のプロセスも貴社に壁打ちしながら進められています。
*
interviewer:
今回の創業融資を経たご経験で、同領域に挑戦している起業家の方に伝えたい気づき等があれば、お願いしたいです。
妹尾さん:
例えば、創業融資について「いまの自分たちが対象になるのか分からない」と悩む方は多いと思います。僕もそうでした。
でも、自分で勝手に線を引かずに、まず相談してみるべきだと感じました。
仮に「もう少し売上を作ってからが良いですね」と言われれば、それはそれでひとつの判断材料になりますし、「この金額ならチャレンジできそうですね」という可能性が見えてくるかもしれない。
特にディープテック領域では、エンジェル投資家さまからのエクイティ等、出資のみしかないと一般的には捉えられがちで、初期の資金計画に悩む方も多いと思うので、選択肢を狭めすぎず、相談することで道が拓けるのではないかと思います。
異分野だからこそ、橋をかけられる──挑戦する人の事例に
interviewer:
最後に、今後の展望について教えてください。
妹尾さん:
私は異業種からこの世界に飛び込んできた人間です。数年前まで、まさか自分がディープテック領域に携わるとは思ってもみませんでした。
でも今は、この素晴らしい技術の価値をどう社会に届けるか。どう人に役立てるか──。
異分野出身だからこそフラットに定義し、培ったビジネス視点で社会や未来につなげていくことが僕の役割だと思っています。
だからこそ、新しい価値への可能性を信じて、引き続き違う立場や分野の人と組むことを大切にしていきたいですし、今後ディープテックに挑戦する人の背中を少しでも押せるような事例になれたら嬉しいです。
*
※本記事は、取材時点の情報です
※インタビュアー・編集:株式会社INQ 遠藤 朱美
※デザイン:高橋 亜美さん
▼本プロジェクトのコンサルタント担当者

片岡優也
1992年滋賀県野洲市生まれ。明治大学法学部卒。
卒業後、営業スキルを鍛えるため、リクルート系大手人材派遣会社にて営業職として勤務。 営業部門で年間表彰を受けるなどトップセールスの記録を持つ。 ビジネスにおいて金融及び法律の知識は必須であるという考えから、行政書士資格を取得する。 前職の営業経験とフットワークを活かし、2年間で200件を超える融資案件を担当。 クライアントの問題解決のために多角的なコンサルティングを行っている。 迅速な対応と丁寧なフォローでクライアントの信頼も厚い。
2匹の猫、一児の父。