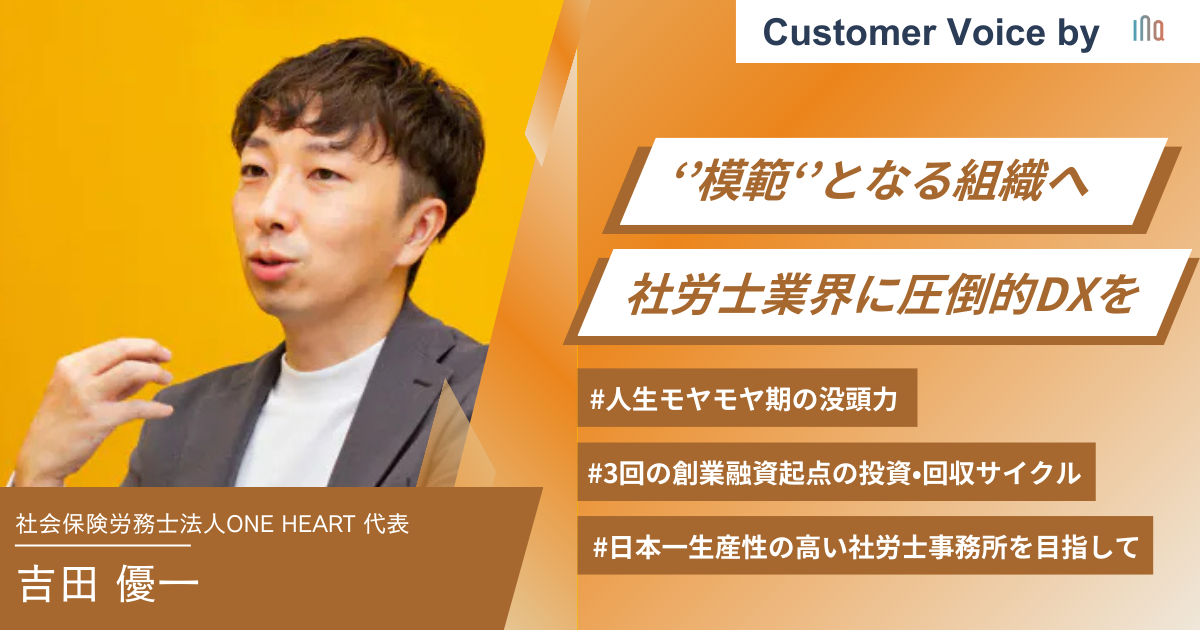株式会社M&Aドットコム
藤澤専之介
軽やかに変化をとらえて、M&A支援をひらいていくー借りられる時に借りておく重要性ー
2025年8月13日
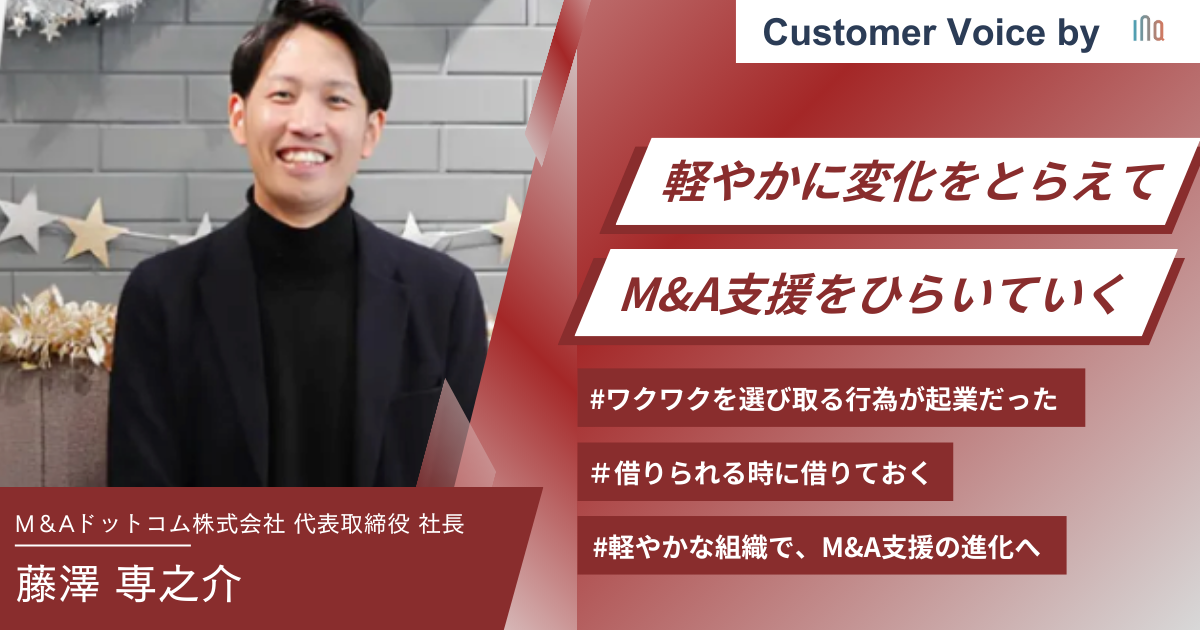
M&A領域で事業を展開する株式会社M&Aドットコム。
セルサイドFA支援とM&A実務のAI化という2軸で、小規模M&Aに新たな選択肢を提示しながら、変化に“軽やかに”対応する組織づくりを進めています。
創業者・藤澤さん は、人材業界での営業・新規事業開発を経て独立。RPA事業での起業とM&Aを経て、再び創業の道へと踏み出しました。
“地に足のついた経営”を実現するため、自己資金とデットによる事業推進というスタンス。
「できること」で勝負しながらも、「ワクワクを優先」してきた道のり。
変化の時代をしなやかに進む、等身大の藤澤さんに、これまでの歩みと見据える未来について伺いました。
藤澤専之介(ふじさわ・せんのすけ)X
1986年生まれ、神奈川県横浜市出身。大学卒業後、繊維メーカー、人材会社を経て、人材大手のインテリジェンス(現パーソルキャリア)に転職。法人営業のマネジメントや新規事業開発等に携わる。2018年にRPA(Robotic Process Automation)の専門会社であるPeaceful Morning株式会社を創業。 2022年、同社を株式会社クラウドワークスにM&Aで売却し、EXITを経験。 この経験を通じてM&Aの専門知識を深め、M&A戦略の重要性を確信する。2024年4月、M&Aドットコム株式会社を創業。M&Aを検討する企業に対し、最適な戦略立案から実行までをサポート。特に、片手FAとして、売り手と買い手のどちらか一方のみをサポートすることで、クライアントの利益を最優先に考えたM&Aアドバイザリーを提供することに強みを持つ。千葉大学 客員研究員も務める。
目次
“ワクワク”を優先した決断――RPA市場への挑戦
interviewer:
まず、藤澤さん のこれまでのキャリアについて教えてください。
藤澤さん :
もともと私はサラリーマン時代、人材業界に長くいまして、ベンチャーでの事業立ち上げの経験後、パーソルキャリアという会社で5年程、法人営業や新規事業開発に携わり、その後会社を辞めて起業しようと考えました。
実はやりたいことがたくさんあったんです。たとえば子育て支援のサービスとか。
ただ、初めての起業だったということもあって、実際会社は辞めたものの、やりたいことをすぐ事業にするのが難しくて、数ヶ月は模索しているような状態でした。
そんな中で、前職の人材業界での経験を活かして、採用に困っている会社の手伝いを頼まれたんですね。その会社がたまたま外資系で、グローバルNo.1のRPAツールを開発している企業の日本法人だったんです。
そこで採用支援をすることになり、当時社員数50人ほどだったのが、半年後には150人規模まで急成長していったんです。
interviewer:
RPA業界の成長を現場で目の当たりにされたんですね。
藤澤さん :
採用担当という立場でその急成長を間近で見て、「これはすごいな」と。たまたま関わったRPAという領域が、確実により伸びるだろうということを実感値を持って捉えられたんです。
interviewer:
なるほど。 そもそも、起業に至った背景にはどのような想いがあったのでしょうか?
藤澤さん :
大手人材会社にいた最後の1年程は、新規事業開発に携わる中で、周りのメンバーが実際に会社を辞めて起業していく方々もいて。「あ、自分にもできるかもしれない」と自然に思えるような環境に身を置いていて、実際にそう思うようになっていったんですね。
そして、正直なところ、当時の自分はこのまま会社の中で、ワクワクするような未来が描ける想像があまりできなかったんです。出世してもあまり面白くなさそうだな、と。
そんな状態で、会社にい続けることのリスクと、辞めて挑戦するリスクを天秤にかけたときに、最終的には「辞めた方がリスクが小さいかもしれない」と思えたのが、決断のきっかけでした。
interviewer:
ワクワクする未来を大事にされたんですね。
藤澤さん :
はい、ワクワクするかどうかがすごく大事で、逆に言えば、本来は飽きたらすぐ次に行きたくなるようなタイプです(笑)
interviewer:
自己理解、大事ですね…!
事業ドメインをRPAに選ばれた背景には、市場の成長スピードとご自身の特性がうまくかみ合っている印象があります。その点について、周囲からのアドバイスもあったのでしょうか?
藤澤さん :
はい、のちにエンジェル投資家として出資していただく方にご相談していて、その方からは「初めての起業なら、やりたいことよりも、できることや伸びている市場で勝負した方が成功確率は高い」と。
当時、自分のやりたい起点で思ったような軌道にのせられていなかったこともあって、「よし、これをやってみよう」とアドバイスを素直に受け入れて決断しました。周りのアドバイスや、自分の経験、タイミングが結果的に重なった意思決定でしたね。

当時のオフィス
行動しながら見出した「できること」起業――そしてM&Aへ
interviewer:
RPA領域での事業はどのように始動していったのでしょうか?
藤澤さん :
最初はとにかくRPAについてのブログを毎日書いてました。
事業仮説のための情報収集も兼ねて、反応をくれた人たちとランチに行ったり、会いに行ったりしていましたね。
そんな活動を2〜3ヶ月続けていたら、自然と業界の知識が深まり、人脈もできてきたんです。途中からはそのブログを“RPA専門メディア”として立ち上げて、より情報を体系的に発信していくようにしました。
interviewer:
その後、どのようにして事業化につながっていったのでしょう?
藤澤さん :
RPAのフリーランスとして働く方に取材した記事を掲載したんですが、それがすごく反響が大きくて。
「このニーズあるかも」と思って、記事の下に“フリーランスで働きたい方はこちら”というフォームをつけたら、1日に2〜3人、登録が入るようになったんです。そこから半年程後に、フリーランスのRPAエンジニア向けのエージェントサービスを立ち上げました。
登録エンジニアは最終的に1000人規模まで増えて、その方々と一緒に、開発や研修・導入後の保守・ライセンス販売など、フリーランスを核にした複数のサービスを展開していました。
ひたすら実践して、業界解像度を上げながら学んでいった感じでしたね。
interviewer:
事業はその後も順調に拡大し、創業から4年後の2022年10月、人材マッチング大手・クラウドワークスとのM&Aでグループ入りされました。その決断の背景には、どんな考えがあったのでしょう?
藤澤さん :
2つの視点がありました。
1つ目は、RPA技術の進化スピードです。
市場への定着フェーズに入るタイミングが想定より早く見えてきていました。もしRPA事業一本で行くなら、市場成長のピークが来る前に、事業成長のスピードをさらに上げてイグジットする必要があると考えました。
もう1つは、自分自身の特性です。
私は「事業をつくること」には強みがあり、成長性にフルコミットしてきましたが、一方で組織力には課題がありました。マネジメント層を採用して組織化を進めるというよりも、業務委託メンバーと共にサービス単位でスピード重視の立ち上げを行うスタイルです。
そのため、仮にIPO(新規株式公開)を目指すなら、RPAのような事業柱をあと2〜3本構築し、経営体制も整備する必要があると感じていました。
こうした背景を踏まえ、自分の特性や得意領域を活かしつつ「成長性を止めない」ためには、M&Aという選択が最適だと判断しました。
interviewer:
なるほど。グループインすることについて、メンバーのみなさまの反応はいかがでしたか?
藤澤さん :
もともと集まってくれていたメンバーは、「この事業が面白い」「お客様に価値を届けられる」といった、事業やコトを基点に関わってくれる人がほとんどでした。
そのため、「引き続きこの事業に関われる」「グループインによってアセットが増え、提供できる価値もさらに広がるかもしれない」といった、前向きな声が多かったです。
interviewer:
会社への所属よりミッションや提供する価値に重きを置く方々を採用できていたからこそですかね。
藤澤さん :
そう思います。M&A後、事業の幅も拡がり、メンバー・投資家の方・お客様含めて、よい意思決定だったと捉えています。
interviewer:
その後、スタートアップのための経営加速クラウドなどを提供する StartPassにジョインされました。
どういった想いで参画されたのでしょうか?
藤澤さん :
自分自身、起業を経験して気づいたこともあり、「もっと起業を身近にしたい」という想いがありました。また、エンジェル投資家の方々に支援していただいた経験から、「起業家を支援したい」という気持ちも強く、そのような活動ができる環境を探していました。
StartPassはまさに起業家支援を幅広く行っている会社で、「ここはすごくいい環境だな」と感じ、ご縁もあってジョインしました。
ただ、実際にやってみると、「あ、自分はやっぱり起業家でありたいんだ」と気づいたんです。
interviewer:
なるほど。一度やってみたことで、自分の“こうありたい”という想いが明確になったのですね。
藤澤さん :
そうですね。自分なりの好奇心やワクワクに、まっすぐ従って動いてきた結果だと思います。
再び起業家へー当事者として感じた想いで、M&A支援をひらく。
interviewer:
現在のご事業について教えていただけますか?
藤澤さん :
大きく2つのサービスを展開しています。
1つ目は、会社の売却を考えている経営者向けの「セルサイドFA(ファイナンシャル・アドバイザー)サービス」です。これは、M&Aの売り手側に立って、その売却プロセスを伴走支援するものになります。特に、私自身の経験を活かして、ITやHR領域の企業様を中心に支援しています。
interviewer:
売り手と買い手の両方を支援する“仲介モデル”もある中で、売り手側に特化したサービスにされた理由は何でしょう?
藤澤さん :
たしかに、現在の日本では、売り手・買い手の双方から手数料を得る「仲介モデル」が主流です。これは、両社のニーズをすり合わせてスピーディーに提案できるというメリットがある一方で、中立性が損なわれるリスクもあります。
一方、FAモデルは売り手からのみ手数料をいただくため、売却価格の最大化など、売り手にとってより望ましい支援が可能になります。ただ、FAは大型M&Aでは一般的なんですが、日本では中小規模の案件が多く、手数料が成立しづらいと言われてきました。
でも、私自身が小規模M&Aの当事者だったからこそ、「たとえ小さな会社でも、売り手に寄り添った支援が必要だ」と強く感じたんです。
このモデルであれば、より多くの事業者さまのリアルなニーズに応えられる。そんな想いから、このスタイルで展開しています。
interviewer:
当事者としての経験が、事業の起点になっているのですね。
2つ目のサービスについても教えてください。
藤澤さん :
2つ目は、M&A実務の自動化を目指すAIツールの開発・提供です。
M&Aって、まだまだアナログな業務が多いんです。たとえば、買収候補の調査や、企業情報の整理、資料のやり取り、各種記録の管理など、細かいけれど時間がかかる作業が山ほどある。
そうした業務をAIやツールで自動化することで、M&Aをもっと効率的に、そして身近なものにしていきたいと考えています。今は、買収を検討している企業の担当者向けに、実務支援ツールを開発中です。
interviewer:
ここ数年で、M&A市場はExitや成長戦略の手段として、かなり広がりを見せている印象があります。
藤澤さん :
そうですね。たとえば、上場企業が新規事業を自前で立ち上げるのではなく、M&Aで外部から取り込む動きが加速していますし、スタートアップ側も連続的に他社を買収して成長していく“ロールアップ戦略”を取る例が増えています。
以前は「会社を売る・買う」って、もっと特別な行為だったと思うんですが、今ではM&Aがキャリアや経営判断のひとつとして、徐々に“当たり前”になりつつあると感じます。
その変化の中で、自分のこれまでの経験や強みを活かせるフィールドだという実感があります。
interviewer:
創業から約1年が経った今、1回目の起業と比べて、経営者としてのスタンスに変化はありますか?
藤澤さん :
ありますね。
今は自己資金とデットを活用して事業を進めていますが、以前よりも“地に足のついた経営”ができていると感じます。
interviewer:
目指す未来や経営スタンスから、自己資金とデットによる事業推進を選択されているのですかね。
藤澤さん :
そうですね。AIなどの技術進化もあり、人手や多額の資金がなくても事業が前に進められる時代になってきています。もちろん、何を選ぶかは目的次第ですが、「人を増やすことで組織が重たくなりすぎるリスク」は避けたかった。
だからこそ、自分たちのペースで、持続可能な形で経営できる体制を大切にしています。
interviewer:
今のフェーズで、経営として最重要と位置づけていることがあれば教えてください。
藤澤さん :
やはり「差別化」です。
他社にできなくて、自社だからこそできることは何か?という問いを常に持っています。M&Aの仲介会社は多くありますが、AIやデジタルをここまで事業プロセスに組み込んでいるところは、まだ少ないと感じています。
その意味でも、プロダクト開発を通じて自社の独自性を磨くことは、今のフェーズでとても重要ですし、同時にその価値をしっかり“伝える”ことも大事にしています。
どう見られているかを意識しながら、外からのフィードバックも活かし、事業全体を回していく感覚です。

「借りられるときに、借りておく」ことの重要性
interviewer:
ここからはファイナンスについてお伺いしたいです。
先ほど、持続可能な経営スタンスとして「自己資金とデットを組み合わせた事業推進」というお話がありましたが、デットを実行していく上で、タイミングやスタンスについては、どのようにお考えでしたか?
藤澤さん :
そうですね、「借りられるときに借りておくことの重要性」だと思っています。
創業期に活用できる創業融資があるうちに、できるだけ手元にキャッシュを持っておきたいという意識は、当初からありました。
当時は、創業からまだ1年というタイミングだったので、1,000万円くらいが上限かなという感覚でいたんです。でも実際には、創業融資で2,000万円を借りることができました。
interviewer:
弊社社担当とのやり取りの中で「もう少し枠を広げていきましょうか」といった話もあったのでしょうか?
藤澤さん :
はい。「可能なタイミングで、よりキャッシュを厚く持っておきたい」という意識が強かったので、「じゃあ、借りられる最大限の範囲で行きたいです」と相談しながら進めました。
結果として、当初想定していた倍の金額を調達できたのは、スタートアップ向け創業期の融資環境が少しずつフレンドリーになってきていると感じた部分でもありますし、何よりINQさんの支援が非常に大きかったと思っています。
interviewer:
その支援というのは、具体的にどのような点ですか?
藤澤さん :
まず、調達プロセスが本当にスムーズだったという点ですね。
僕自身、一度借入経験があるとはいえ、やはりゼロから書類を整えたり金融機関とやり取りするのは大変なので、「期間限定のCFO」がそばにいてくれるような感覚でした。
もちろん手数料は発生しますが、それ以上に時間的にも精神的にも、自分だけでやるよりはるかに効率が良く、お願いする価値があると感じました。
interviewer:
ありがとうございます。今回のご経験を踏まえて、気づいたことや、今後に活かしたいと感じた点はありますか?
藤澤さん :
強いて言うなら、「この規模感で借りられるなら、もっと早く知っておきたかったな」という点ですね。
前職での経験から「調達についてはある程度わかっているつもり」でしたが、制度や融資環境は常にアップデートされています。だからこそ、自分の知識に頼りすぎず、情報をキャッチアップし続けることの大切さを実感しました。
そういう意味でも、専門家に任せることで時間も手間も節約でき、一石二鳥だったなと思います。
軽やかな組織で、M&A支援の進化へ
interviewer:
会社として描いている未来や、今後のご自身についてお聞かせいただけますか?
藤澤さん :
会社としては、M&A領域で「ニッチなトッププレイヤー」になっていきたいと考えています。
どの領域でトップを目指すかは、これからより見極めていく必要がありますが、「この領域ならあの会社だよね」と言ってもらえるような、専門性のある立ち位置を築いていきたいですね。
その実現に向けて、組織としては「変化に強い組織」でありたいと思っています。今は本当に世の中の変化が激しい。だからこそ、組織も“軽やかに”動けるようにしたい。大きな設備投資をしなくても、小さく試して、反応を見ながら素早く動くという価値観を大切にしています。
interviewer:
今のチームで、それを体現するために意識されていることはありますか?
藤澤さん :
たとえばAIに対しても、「何ができるか/できないか」ではなく、「どう使えるか」という視点で見るようにしています。
1年後には自分の仕事の大半がAIに置き換わっているかもしれない──
そんな前提でいると、今やっていることへの執着がいい意味で減るんです。自然と「できない理由」ではなく、「どうやったらできるか」を考えるようになります。
interviewer:
自身のその姿勢が、組織全体に伝わる身体知のようになっているのかもしれませんね。
藤澤さん :
ありがとうございます。
あと、個人的な哲学として「勤勉なサボり魔」でいたいと思ってるんです(笑)。
interviewer:
それはどういうことでしょう?…
藤澤さん :
「どうすればサボれるか」を真剣に考える、ということです。
サボるために自動化や効率化を徹底的に追求する。その結果、業務が改善されて、提供したい価値に変換されたり、最大化されていくと思っています。
技術の進化が日進月歩な今の時代は、自分のこの性質にすごく合ってると感じますね。
interviewer:
結果として生まれた余白の時間を、どう捉えるか。仕事以外のことにも通じそうです。
藤澤さん :
本当に、1年後ですら予測できない時代なので、10年後なんてもっと想像がつきません。
だからこそ、今を楽しむこと、「どう働くか」と同時に「どう生きるか」という視点を持っていたい。好奇心やワクワクを大切にする自分でありたいし、そういう価値観を共有できる会社でありたいと思っています。
*

※本記事は、取材時点の情報です
※インタビュアー・編集:株式会社INQ 遠藤 朱美
※デザイン:高橋 亜美
▼本プロジェクトのコンサルタント担当者

片岡優也
1992年滋賀県野洲市生まれ。明治大学法学部卒。
卒業後、営業スキルを鍛えるため、リクルート系大手人材派遣会社にて営業職として勤務。 営業部門で年間表彰を受けるなどトップセールスの記録を持つ。 ビジネスにおいて金融及び法律の知識は必須であるという考えから、行政書士資格を取得する。 前職の営業経験とフットワークを活かし、2年間で200件を超える融資案件を担当。 クライアントの問題解決のために多角的なコンサルティングを行っている。 迅速な対応と丁寧なフォローでクライアントの信頼も厚い。
2匹の猫、一児の父。