社会保険労務士法人ONE HEART
吉田 優一
‘’模範‘’となる組織を。社労士業界に圧倒的DXをー3回の創業融資起点の投資・回収サイクルー
2025年8月28日
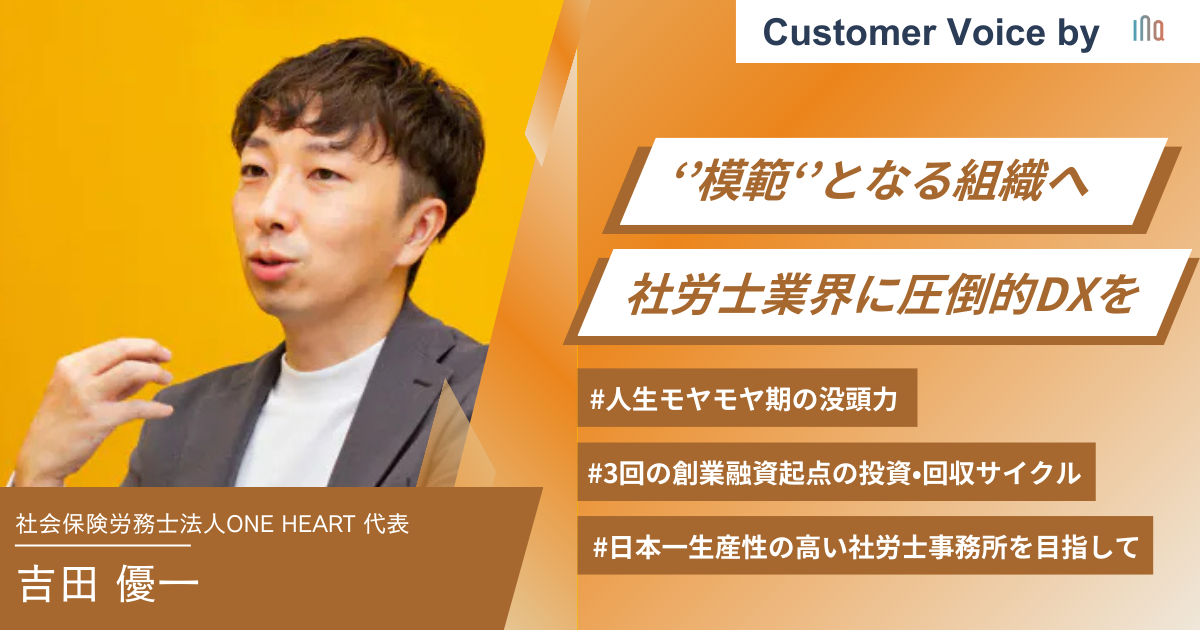
全国リモート体制で事業を展開する、社会保険労務士法人ONE HEART。
労務DXとクラウド導入支援を軸に、成長企業の“組織の土台”を整える伴走支援を行っています。
代表の吉田さんは、大学中退後“人生モヤモヤ期”に、読書に没頭した日々を経て、社労士の道へ。
自社の採用や組織づくりにも徹底してこだわり、成長への投資と現金余力の両立を実現しながら顧客の“模範”となる事務所づくりを実践しています。
就職を恐れていた時期から、どのように「日本一生産性の高い社労士事務所」を目指すまでに至ったのか。その歩みを伺いました。
社会保険労務士法人ONE HEART 代表 吉田優一 / X
慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。
こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。自社経営においても、顧問先への支援においても、クラウドサービス「マネーフォワード」を中心とした最新の労務管理システムを積極的に導入し、働きやすい職場環境の整備や労務の効率化をサポート。
目次
人生モヤモヤ期からうまれた「働くこと」への関心―読書の没頭から辿り着いた社労士の道
interviewer:
まず、吉田さんが社労士になるまでの経緯について教えてください。
吉田さん:
私は大学を中退して、しばらく「モヤモヤ期」を過ごしていました。
中高一貫校に通っていたんですが、あまり勉強してこなかったんですよね。それでも一念発起、必死に勉強して慶應義塾大学に進学しました。とはいえ、ちゃんと大学選びをしたわけではなくて、偏差値が高いからという単純な理由で選んでしまったんです。
interviewer:
実際に入学してみて、違和感が生じたのでしょうか?
吉田さん:
いい大学だと思うんです。でも自分にはちょっと合わなかったんです。
大学という組織に“ただ学ぶために通うもの”というイメージで入学したので、実際のカルチャーとのギャップに戸惑いました。結果、大学には馴染めず、だんだんと通えなくなって、最終的には中退しました。
そこからは、就職も怖くなってしまって……。今振り返ると、無名ではない大学だったので、ニコニコしながら、面接受ければなんとかなったはずです。でも、逆に真面目に考えすぎてしまって、身動きが取れなくなってしまったんです。
しばらくは家に引きこもっていて、人生のモヤモヤ期でした。ただ、現状を変えたい気持ちも強くありました。
そんな時、ふと「本が読める」と思ったんです。
それまでは読書が苦手だったんですけど、なぜか集中できて。そこから1日2〜3冊というノルマを決めて、ひたすら自分探しの旅のように読書する生活に切り替えました。1年で2000冊以上は読んだと思います。
interviewer:
2000冊!没頭する力を感じます。どんなジャンルの本を読まれていたんですか?
吉田さん:
哲学書、経営本、自己啓発等です。当時、大学中退からの背景もあり「自分の人生がうまくいかないのは社会のせいだ」と思っていた節もありました。
そんな中で出会ったのが、『労働経済改革の経済学』という本です。その中で語られていた解雇規制の話に強く惹かれました。「ああ、自分が就職できないのは、解雇規制が強いからなんだ」とか、そんな風に本気で思っていましたね。
interviewer:
その関心が、“労働”起点の社会構造に目を向けるきっかけになったのですか?
吉田さん:
まさにそうですね。その本を読んで、働くこと自体に強い興味を持つようになりました。ちょうどその頃、いとこが不動産鑑定士の資格を取ったり、知人に社労士がいたりと、資格という選択肢が自分の現実に近づいてきていて。「社労士ってなんか面白そうだな」と思って、資格取得にチャレンジすることにしたんです。
interviewer:
社労士の資格を選ばれた理由は、何でしょう?
吉田さん:
先ほど紹介した『労働経済改革の経済学』の本で、日本の労働市場には、ゆがみがあるということがわかったので、これからは労務にビジネスチャンスがあると思い社労士を目指しました。
だいたい1年半ぐらい猛勉強しました。もう人生賭ける想いでやってました。
“顧客と共に歩む”を体現する、実務と組織のかたち
interviewer:
結果、無事資格を取得されたのですね!その後、社労士事務所で働かれたのですか?
吉田さん:
はい、まずは社労士として勤務経験を積みました。2つの社労士事務所に所属して、合計で7年半ほど働いていました。
1社目は地場密着型の、いわゆる一般的な社労士事務所で、 2社目は「共同経営」という形でご縁をいただきジョインしました。
結果的に、共同経営の思想がなかなかフィットせず、辞めたのですが、社労士として1社目で基本的なことを学んで実践し、2社目で労務相談やコンサルティングを学んで、体得できた経験でした。
interviewer:
その後、起業される経緯ですね。どんな想いがきっかけとなったのでしょうか?
吉田さん:
もともと「労務管理のプロフェッショナルになりたい」という気持ちはあったんですが、ある時から「自分の組織をつくり、その労務管理をする。つまり経営する人になりたい」と思うようになったんです。
大きな影響を与えたのが、とあるプレゼンを見たことでした。
株式会社ヒトカラメディアの元CFO 乙津さんが、SmartHRなどのクラウドツールをどう連携させているかの内容です。従来のレガシーなオペレーションでは、社労士が手作業で生年月日や住所を入力したり、同じ情報を複数の労務管理ツールに何度も打ち込んだりしていて、非常に非効率なんです。でも、クラウドツールでデータがつながると、例えばSmartHRに登録した情報を、API連携でKING OF TIMEやマネーフォワードに転記できる。手入力がなくなるだけで、業務効率は飛躍的に上がります。
当時、その話を聞いた時「これだ」と思ったんです。
労務業界は、DXの浸透が他業界と比較しても低いと捉えていました。自分自身が社労士として実感してきたからこそ、クラウドによる生産性向上のポテンシャルとそれを自分がやる意味があると思えました。

interviewer:
そして、2021年に現在のONE HEARTを創業されたのですね。現在の事業内容について教えてください。
吉田さん:
大きく分けて3つの柱があります。
1つ目は労務相談、2つ目は社会保険などの手続き代行、3つ目が給与計算の代行です。これらは単体でご依頼いただくこともありますが、多くの企業様とは、3つをセットにした顧問契約として関係を築いています。
さらに、私たちはクラウドツールの導入支援にも注力しています。たとえば、紙のタイムカードやエクセルで運用されている企業様に対して、クラウド勤怠やクラウド給与の導入を支援し、その前提となる就業規則やルール整備から運用フェーズまで、一気通貫で伴走しています。
顧問先の多くは「会社をより良くしたい」「成長フェーズに合わせて労務体制も進化させたい」といった強い意志を持っている企業ばかりです。だからこそ、私たちもただ制度や仕組みを“入れるだけ”で終わらせず、それが実際に使えるようになるところまでを意識して支援しています。
interviewer:
まさに、支援する企業と並走しているイメージですね。そうした在り方を、社内でも体現されている印象があります。組織づくりにおいて、特に力を入れていることはありますか?
吉田さん:
やはり、採用ですね。
「どんなチームで、どんな価値観で働いているか」が伝わるよう、Webサイトやコンテンツの見せ方にもこだわっています。Podcast番組「10分で労務がわかるラジオ」なども、その一環です。
また、働き方も、創業から1年ほど経ったタイミングで、完全リモートに切り替えました。全国どこにいる方でも採用できるようになったことで、優秀な方と出会える確率が格段に上がりました。リモートでも関係性が構築できるよう、毎朝の全体ミーティングや、月1回の1on1面談を欠かさず実施しています。
良い組織づくりにおいて最も大事なのは、“人”だと思っています。
やる気のある人がやる気のない人と働くことほど、モチベーションを削ぐことはありません。だからこそ、妥協しない採用と日々のコミュニケーションが、組織の土台になると考えています。
interviewer:
さまざまな企業の労務に関わってきたからこそ、見えてきた理想と反面教師もあるのでしょうか?
吉田さん:
ありますね。
社労士として多くの労使トラブルに向き合ってきましたが、そのほとんどが「会社がやるべきことをやっていない」ことに起因しています。
極端ですが、未払い残業代やパワハラも、採用や教育に投資しない、制度と運用がセットで整っていない……そういった会社側の課題が根本にある。
だからこそ、私たちは日々の運営の中で、「やるべきことをきちんとやる」を徹底しています。たとえば、毎朝の全体会議を実施したり、月末の1on1定例面談では、困っていることはすべてヒアリングし、頑張ってくれたことにはしっかり称賛を伝えるようにしています。 地道ですが、そういった姿勢の積み重ねが、強くしなやかな組織をつくると思っています。
優位性強化と集客投資で成長加速へ―3回の創業融資からの投資・回収サイクル
interviewer:
ここからはファイナンスの話を少しお伺いできればと思います。創業から現在までの資金調達と主な活用目的について、教えていただけますか?
吉田さん:
創業前後に日本政策金融公庫からの融資を受けて、その後に芝信用金庫から追加で調達。そして直近、再び公庫から800万円で3回目です。
今回の資金使途は、「運転資金」ですが、大きく分けて2つの目的があります。1つは、会社としてより優位性を高めていくため、コンサルティング会社と組んで計画策定・実践を進めること。もう1つは、集客力をさらに強化するためのWebコンテンツやマーケティング投資です。具体的には、ポッドキャスト等のすでにあるコンテンツをSEOコンテンツとして再活用するなど、集客の導線を強くしていていく、さらに資産化する方向ですね。
もともと我々もアウトソーシングサービスを提供している立場なので、自社が成長していく上で必要だけど、苦手な領域はプロにお願いする、という考え方を徹底しています。ファイナンスも同様で、自分たちが手を出すより、信頼できるパートナーに任せる方が圧倒的に効率的ですし、実際に結果も出ています。
振り返ると、過去の融資はすべてINQさんにご支援してもらったんですよね。今回の融資に関しても、担当してくださった片岡さんの仕事ぶりは本当に早くて。「非常に仕事の早い男」だと思いましたね(笑)
interviewer:
同感です…!
これまで3回の融資支援を受けられてきたご経験を踏まえて、もしINQを「ぜひおすすめしたい」と思う企業様があるとすれば、どんな会社でしょう?
吉田さん:
成長志向が強いあらゆる会社におすすめしたいですね。
INQさんを知ったのは、代表の若林さんのXがきっかけでした。自分からDMを送り、やり取りがスタートしました。支援されてきた多くの経験から、攻め・守り両方から資金調達と経営視点でサポートいただける印象です。
成長志向の企業にとって、創業期から未来の成長のために調達ができる環境をつくっておくことは不可欠だと思います。 事業上の選択肢が広がるし、不測の事態にも対応できる。資金があれば、必要なタイミングで、必要な投資に踏み切れますからね。
interviewer:
ありがとうございます。自社の財務戦略につながる点もありますか?
吉田さん:
はい、当たり前ですがどれだけいい戦略を立てても、キャッシュが尽きたら会社は終わりです。ゆえに、運転資金としての“安全弁”の確保は注視しています。現預金残高を常に高水準で保つようにしていて、資金調達はそのための保険的な意味合いもあります。
また、土台として企業経営の「調達→投資→回収」という3つのステップを基本として「どこから資金を調達し、どこに投資するのか」「投資したお金がどのような効果を持つのか」は常に意識しています。
今回の「投資」は集客の強化でしたが、次は「人材」がテーマです。スタッフのキャリア形成や報酬の向上に取り組んでいきたいと考えています。
「日本一生産性の高い社労士事務所」を目指して―組織から社会を変えられる
interviewer:
今後、会社として実現していきたい未来について教えてください。
吉田さん:
今後も変えずに大事にしたい軸が、「お客様の模範となる会社であること」です。
他社の労務を支援する以上、自分たち自身がちゃんとした組織であることが絶対条件だと思っています。成長できる環境を整え、メンバーがそれぞれのキャリアを実現できていて、実際にやっていることを自信を持って語れる――そんな姿を見せることが、支援の説得力にもつながると考えています。
そして、もう一つ掲げているのが「日本一生産性の高い社労士事務所になること」です。
interviewer:
明確な目標ですね。そこにはどのような想いがあるのでしょう?
吉田さん:
社労士業界では、人が増えるほど利益が下がる、サービス品質が落ちるという構造があります。でも、しっかりと工数分析をして、ムダを減らしていけば、働く人にも顧客にも持続可能なサービスが提供できるはず。
自社で試行錯誤し、うまくいったことはお客様にも共有する。単にノウハウを渡すのではなく、「こうすれば実現できますよ」と再現性を持たせて届ける。それが、社労士としての仕事だと感じています。
最終的には、良い組織が増えれば、良い職場が増える。良い職場からは、良いサービスが生まれる。そうした循環を、少しずつでも社会に広げていきたい。
まずは、自分たちが“模範となる会社”であること。
その日々の積み重ねこそが、社会全体の変化にもつながっていくと信じています。
*

※本記事は、取材時点の情報です
※インタビュアー・編集:株式会社INQ 遠藤 朱美
※デザイン:高橋 亜美
▼本プロジェクトのコンサルタント担当者

片岡優也
1992年滋賀県野洲市生まれ。明治大学法学部卒。
卒業後、営業スキルを鍛えるため、リクルート系大手人材派遣会社にて営業職として勤務。 営業部門で年間表彰を受けるなどトップセールスの記録を持つ。 ビジネスにおいて金融及び法律の知識は必須であるという考えから、行政書士資格を取得する。 前職の営業経験とフットワークを活かし、2年間で200件を超える融資案件を担当。 クライアントの問題解決のために多角的なコンサルティングを行っている。 迅速な対応と丁寧なフォローでクライアントの信頼も厚い。
2匹の猫、一児の父。


